2人目を妊娠中に夫の転勤が決まり、上の子をどうするか、引越しをどうするか、絶望的になったけど、なんとか乗り切った時の体験談をまとめました。
転勤族ママは、ただでさえいつ異動の辞令がでるかヒヤヒヤ。
それがよりによって出産予定日と異動辞令日が重なるなんて、どう乗り切ればいいか考えていたら、不安しかないですよね。
実は、私も2人目を妊娠中に夫の転勤が決まり、出産予定日と県外への引越しがもろに重なりました。
人生最大の出産というイベントに長距離の引越しが重なっても、なんとか乗り切れた方法と対策を4つのポイントに分けてご紹介します。
我が家の場合は、実家から母が出産から引越しまで手伝いに来てくれたので、なんとかなりましたが、頼れる人がいない場合の支援サービスも合わせてご紹介しています。
この記事を読めば、同じ状況で不安になっている転勤族のパパママの頭がすっきり整理されますよ。
出産と転勤が重なったら安全で余裕のあるスケジュールが大切
出産と転勤が重なった時に考えなければならないことがたくさんあって、本当にパニックになりますよね。
我が家の場合は、実家がどちらも遠方で里帰り出産しないため、上の子をどうするかも悩みの種でした。
臨月の引越しより出産後の引越しを選ぶ
我が家の場合は、出産予定日が2月末。
東海から北陸への辞令が出た1ヶ月後の3月頭が着任日だったので、ほぼ出産予定日と着任日が重なっていてどうしたものかと頭を抱えました。
とにかく臨月での引越しは避けたかったので、色々と夫婦で考えて、会社に相談したり、スケジュールを組んだ結果、なんとか出産と引越しを乗り切ることができました。
| 実際の日付 | スケジュール |
|---|---|
| 2月1日 | 辞令が出る |
| 2月28日 | 出産予定日 |
| 3月1日 | 異動着任日 |
| 3月5日 | 実際出産した日 |
| 4月9日 | 実際引越した日 |
実際のスケジュールを見ると、夫が着任した直後に次女は産まれています。
やはり、予定日ちょうどには産まれませんでした(泣)
引越し日は、出産予定日の前後かなり余裕をもたせて決めた方がママも安心ですよね。
頼れるところはとにかく頼る
我が家は実家がどちらも遠方だったので里帰り出産せずに産むことにしていました。
里帰り出産ではない場合、1番重要になってくるのは実家やお友達など手伝いに来てくれる人がいるかどうかです。
うちの場合は私の実家から両親が手伝いに来てくれたので、夫は先に転勤先に着任することにしました。
手伝いの方の有無で家族の動き方は大きく変わるので、交通費をこちらが負担してでも来てもらえると心強いです。
それでは、具体的にどうやって乗り切ったのか詳しくまとめているので、参考になれば嬉しいです。
秘訣①| 出産に合わせた引越し日を会社と交渉する
 引越し日は、着任日に合わせるのが一般的ですが、出産が重なると話は別です。
引越し日は、着任日に合わせるのが一般的ですが、出産が重なると話は別です。
できるだけ、赤ちゃんにも妊娠産後のママにも負担のかからない引越しにする必要があります。
我が家の場合は、里帰り出産ではなく、母に手伝いに来てもらうことにしました。
- 1人目の時も里帰りしなかった
- 実家が遠方で赤ちゃんを連れて買えるのが大変
- 1人目の時と同じ産院で産みたかった
これで出産することに関しては、不安が取り除かれたので、引越し日を考えます。
引越し日を考える時のポイント3つ
ポイント①|臨月では産院を変えられない。
引越し先で産むことになった場合、健診で通っていない臨月の妊婦を受け入れてくれる産院は少ないです。
そして、まだ何も知らない土地で、ほとんど通ったことのない病院で産むのは、とても不安なものです。
ポイント②|臨月で引越しは、母体に負担がかかる。
引越しは、妊娠していない身体でも、相当疲れます。
これまでの引越しでも、引越した後熱を出したり、疲れで体調を崩していました。
それが臨月の妊婦では、たとえ手伝いをしていなくても、何かと動いてしまうため、負担は相当かかりそうです。
ポイント③|産んでからの引越しでも、すぐには無理!
2人目だと産後の回復は早いかもしれませんが、それも産んでみないとわかりません。
赤ちゃんも、長距離の移動は負担がかかります。
これらの不安が解消できないと、前に進めない状況でした。
要望をまとめて会社に相談
- 産院は変えられない
- 夫は着任日に移動し、家族は出産後に引越したい
- 赤ちゃんがせめて生後1ヶ月になってから引っ越したい
出産と引越しと異動が重なったなら、会社と交渉するのが1番です。
異動は会社から辞令が出るもの、引越し費用も会社が負担、異動日は決まっている。
そうなると、もう会社と相談しかないです。
- 出産する産院はもう変えられないため、家族は出産してから引越し
- 夫は先に着任する
- 引越しは、赤ちゃんの長距離移動による負担を考慮し、最短で着任してから1ヶ月後
辞令は拒否しないし、できる限り家族も対応するけど、最低限これだけは配慮してほしいというスタンスで相談することにしました。
夫の会社は比較的社員の事情を元に、柔軟に対応してくれます。
そのおかげで、要望以上の回答を得ることができました。
- 本人は辞令通りの着任
- 家族は出産後3、4ヶ月後でも引越し可
- 引越し先は本人が手配
- 引越し先入居までは、マンスリー利用(会社負担)
ありがたい回答です。
引越しを手伝ってくれる母の滞在期間があまり長くならないよう、当初考えていた通り、産後1ヶ月後に引越しをすることにしました。
手伝いに来てもらえるかどうかにもよりますが、とにかく会社と相談しないことには話が進まないので、こちらの状況や要望をしっかり伝えることが大事ですね。
秘訣②| 上の子の預け先を考える
次に問題となったのが、夫は先に着任しているので、出産となった場合、入院中に上の子をどこに預けるかです。
上の子を預ける上で心配だったのが、まだ寝かしつけはママじゃないと泣くし、1週間以上ママと離れたことがないのも不安材料でした。
また、長女はかなりの食べ物アレルギーがあり、ちゃんと食事管理ができる信頼できる人じゃないと預けるのが難しい状況でした。
そうなんです。
なんなら転勤のことより、入院中の上の子のことが、1番心配でした。
結局、うちの場合は私の母が出産から引越しまで付き添ってくれていましたが、寝ている時に泣いてないからしらと、入院中はドキドキしていました。
しかし、楽しそうに遊んでいる写メは送られてくるし、夜寝る時もすんなり寝てくれたそうです。
拍子抜けでした。
子供なりに状況を理解して、頑張ってくれていたのだと思います。
逆に、そんなに長い期間離れたことがなかったママの方が、寂しくて病院で泣いちゃいました。
我が家は親に来てもらえましたが、様々な事情があると思いますので、上の子の預け先の選択肢がどれほどあるのかまとめてみました。
全部で6パターンあるので、ご家庭の事情に合った預け先が見つかるといいですね。
上の子の預け先①実家・義実家
実家に頼るのが1番気が楽ですし、把握できている部分も多いので安心ですよね。
義実家も関係が良好で、顔を合わせることが多いなら、自分の親が頼れない場合は、とにかく頼れるところに頼るのがベスト。
上の子の預け先②保育園の一時保育
通っていなくても、保育園の一時保育を利用することができます。
この場合、送り迎えが可能か、夜は誰が上の子をお世話するのかを考える必要があります。
親が送迎して、夜はパパが面倒みるなど、家族総出で協力できれば、利用できそうですね。
上の子の預け先③行政の緊急保育
切迫早産などで、予定外に預けなければならなくなった時など、頼る先もなく、預け先に困ったら、とにかく行政に相談しましょう。
緊急保育で預け先を考えてくれたりしますので、親戚や友人に頼れないからと言って諦めず、自治体に相談してみましょう。
上の子の預け先④産院の子連れ入院
上の子も一緒に入院が可能な産院であれば、一緒に病院で過ごすこともできますね。
ただ、他に頼れる先があるなら、この選択肢は避けたいところです。
産後クタクタのところ上の子の相手をしたり、夜中も頻回授乳で睡眠時間が無い時に、身体も心も休まらないのは、非常に大変です。
また、赤ちゃん返りで上の子がいつも以上にかまって状態になる可能性もあるため、産院の子連れ入院は最後の選択肢にするのがおすすめです。
上の子の預け先⑤ママ友
信頼できるお友達で、同じくらいの年頃のお子さんがいらっしゃるなら、お願いするのも手かもしれません。
合宿してるみたいで、子供も喜びますし、同じくらいの年齢の子育てをしているので、扱いも慣れていると思います。
ただ、負担はかかると思いますので、後日改めて何かお礼をするといいですね。
上の子の預け先⑥パパ
意外な盲点は、パパが休むこと。
転勤の引き継ぎをひと通り済ませた後なら、できるかもしれませんね。
寛大な会社なら育休明けからの着任も可能かもしれません。
1ヶ月なら会社も大きな影響なく、逆に男性の育休取得の事例ができて、会社的にも好印象かもしれませんので、交渉してみる手もあります。
パパが仕事が忙しくて頼れない場合、1人で悩んでしまうかもしれません。
2人目の出産は、とてもママ1人では乗り切れないことです。
家族だけでなく、友人や行政機関も含めて、様々な選択肢があることを忘れないでください。
秘訣③|引越しはおまかせコースで楽をする

上の子がイヤイヤ期で、赤ちゃんがいて、引越しもしなければならない。
なんだか聞いてるだけで、地獄のようですね。
しかし、我が家はそこまでひどい地獄絵図にはなりませんでした。
それは、引越し業者に全てを任せたから!
引越し業者におまかせするコースを選ぶ!
引越し費用は会社もちなので、我が家はアート引越センターのおまかせパックフルコースを申し込みました。
急な引越しや小さい子供がいる方向けの、小物の荷造りや荷解きまでしてもらえるサービスです。
・基本コース→荷造り・荷解きなし
・ハーフコース→荷造りのみ
・フルコース→荷造り・荷解きあり
このようなコースは、アート引越センターだけではなく、他の引越し業者でもあります。
荷造り・荷解きまでしてもらえるだけでなく、最後に新居の掃除や照明の取り付けなどもしてもらえる「10分間サービス」がついてます。
・らくらくAコース→荷造り・荷解きあり。10分間サービスつき。
・らくらくコースプレミアム→らくらくAコースに、ダスキンお掃除サービスで新居の掃除を3回してもらえる。
様々なサービスがあるので、頼れるところは頼りましょう。
全部お任せしたので、非常に楽だったのですが、少し残念だったことがあります。
それは、当たり前ですが、荷造りと荷解きはそれぞれ別の方がやるので、完全に元通りに小物は戻してもらえないということです。
これは致し方ないことなので、実際の自分の作業量を考えたら我慢できました。
また、間取りが変わり、自分で荷造りも荷解きもしていないので、新居でアレがないコレがないなど、しばらく探し物ばかりしていました。
物件探しで気を付けたこと
物件探しは、先に着任して現地入りしている夫に任せました。
産後間もないので、家族は物件を見に行けません。
- 物件の間取り図を探している段階からもらう
- 内見するときは、ビデオ通話でつないで、一緒に水回りなどチェックする。
- 契約後は、カーテンを先につけておくためにすぐ採寸してもらう。
洗濯機が置ける幅なのか、ベランダは子供が出ても危なくないのか、ビデオ通話でつないで、ママ目線で物件チェックをするのは大事です。
また、カーテンの手配などは、夫が1人で動けるうちに、やってもらいました。
物件探しの条件は、通常の物件探しの条件とあまり変わりませんが、気を付けたことが2点あります。
- 生後間もない赤ちゃんがいるため、小児科が近くにあるか
- 簡単に買い物に出られないため、近所にスーパーがあるか
身動きがとれない状況でも、なんとか乗り切れるよう、小児科とスーパーの位置だけは重視しました。
秘訣④|産後は頼れるサービスをフル活用
産後1ヶ月ほどは、安静にしていた方がいいと一般的に言われています。
とはいえ、2人目ともなると上の子のお世話もあるので、安静にしていられません。
私の場合は2人目の出産が自然分娩だったからか、産後の回復も早かったです。
母の手伝いもありましたが、洗濯や簡単な掃除は、普通にできてました。
しかし、手伝いもない!簡単に出かけられない!買い物できない!というママもいるはずです。
産後乗り切るのに、使えるサービスをご紹介していきます。
産後ヘルパー・家事代行に頼る
頼れる家族がいない場合などは、頼れるサービスがあります。
名古屋市だと産後・産後ヘルプ事業をやっているのでサポートしてくれるサービスを紹介してくれます。
ご自身の自治体でもやってないか、確認してみるといいかもしれません。
民間でも、家事代行サービスがあります。
自分に合ったサービスを検討してみましょう。
ネットスーパー・宅配サービスを活用する
産褥期だけの利用でもいいと思います。
産後は、結構動けると思っても、疲れやすかったりします。
買い物は、帰りに重いものを持つので、赤ちゃんと荷物では負担が大きいです。
個人的には、妊娠中から利用しておいて、サービスに慣れておくことをおすすめします。
◆素材にこだわるならパルシステム
◆食事作りを楽にしたいならヨシケイ
◆ミールキットも人気のオイシックス
まとめ|出産と引越しが重なったら頼れるところは頼る!
ママとしては、転勤・引越し・出産が重なって不安しかないかもしれません。
しかし、核家族化が進んで、転勤族も大勢いる時代なので、行政も民間も様々なサービスがたくさんあります。
ママ1人が頑張るのではなく、家族や友人、行政・民間、みんなを巻き込んで乗り切れるといいですね。
- 引越し日は会社と交渉する
- 上の子の預け先は選択肢をまず知る
- 引越しは業者はお任せする
- 産後は頼れるサービスをフル活用する
費用との相談もあるかもしれませんが、今使わないでいつ使うお金だ!と思って、まずは家族みんなが安心して乗り切る方法を見つけてみてください。
また、新しい土地の観光をしたり、新しいママ友ができたり、乗り切って良かったなと実感できることがきっと増えてきます。
私もなんとか乗り切ったら、子育てしやすい場所で子供の友達もすぐできて、自分ものんびり楽しく過ごせています。
今大変な方も、前向きに捉えられるといいですね。
今不安を抱えているママも、無事乗り切って、元気な赤ちゃんを迎えてハッピーに過ごせることをお祈りしています。
どうしても出産後に上の子に手をかけられない時間はこどもちゃれんじに頼っていました!

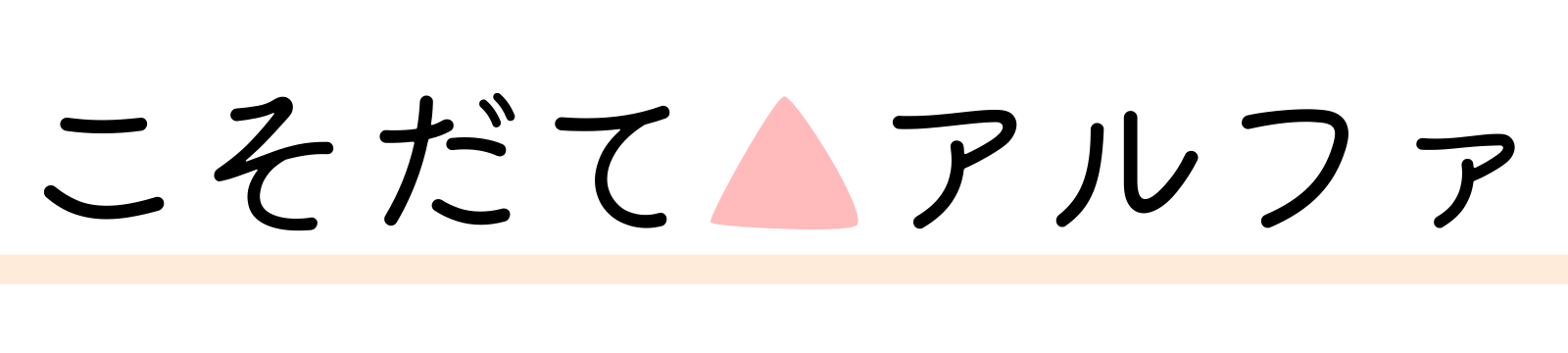


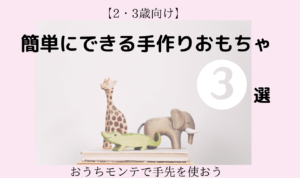






コメント